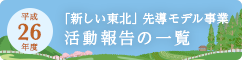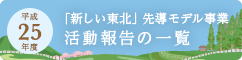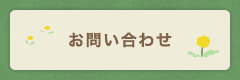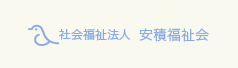「新しい東北」先導モデル事業
活動報告
障害理解・農業体験(大学生)
- 日 時
- 2015年3月12日(木)・13日(金)
- 参加者
- 相模女子大学 栄養科学部 健康栄養学科 2年生 3名
- 場 所
- Kふぁーむ
相模女子大学・本宮市・財団法人農村開発企画委員会の三者が立ち上げた「"水と緑"広域交流連携協議会」の元気な地域づくりの協力・交流システムの一環である「地域協働活動」。都市と農村のニーズを結びつけ、両者の共生・対流を一層推進すると共に、魅力あふれる農村の活性化や活力ある若者の取り組みを支援し、都市と農山村の交流を通じた新たなビジネスを展開する目的。今回、訪れた学生達にKふぁーむの特色や魅力を知って頂き、全国に発信してもらいたいと考え、プログラムの実現に至った。
障害者や高齢者とのふれあいから学ぶこと。共生社会体験。
将来、栄養士を目指す学生たちはKふぁーむで実践している共生事業の取り組みを2日間の日程で体験した。昨年、農業体験で受け入れた2名の生徒が今年もKふぁーむを訪れてくれた。初日の朝、農場長から「栄養士は人の食を預かり責任が大きい。栄養学以外にも様々な業際を学ばなくてはならない」という言葉を学生に伝えた。学生たちは動物達の世話、農作業、Kふぁーむ産の食材を支える障害者達との共同作業(牧柵のペンキ塗り、Kふぁーむ産のたまごを使ったスコーン作り)、障害理解学習、高齢者への介護を体験し、各現場で障害者や高齢者と関わりのある飼育員、精神保健福祉士、心理士、介護福祉士等からの共生事業や障害についての説明、障害を乗り越え社会復帰をしているピアサポーターからリカバリーストーリーを真剣に受け止めることで、各々が考え障害や共生について理解を深める事ができた。積極的に障害者へ笑顔で話しかける姿も見られた。参加した学生は、障害はみんなが理解すべき大切な事。正しい知識で、偏見をなくし風邪と同じように当たり前になって欲しい。大学では学べないことが体験出来、良い機会だった。またKふぁーむを訪れたい。と感想を述べた。今回の体験で障害について学生ひとりひとりが新しい価値観と出会う事が出来たのだと感じた。人の役に立ちたいという思いがあり栄養士を目指す学生達、今回体験し感じ学んだことを、将来何かしらの形で活かし、役立ててもらいたい。